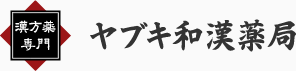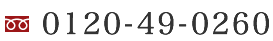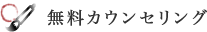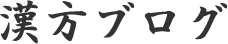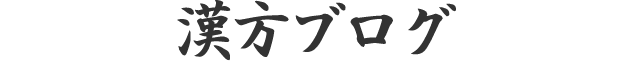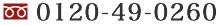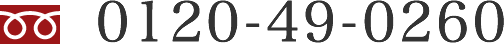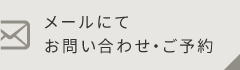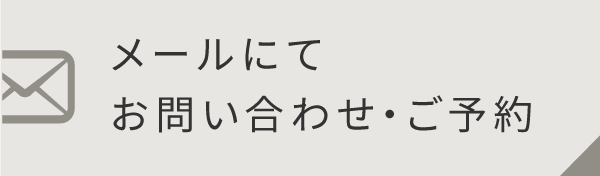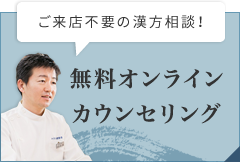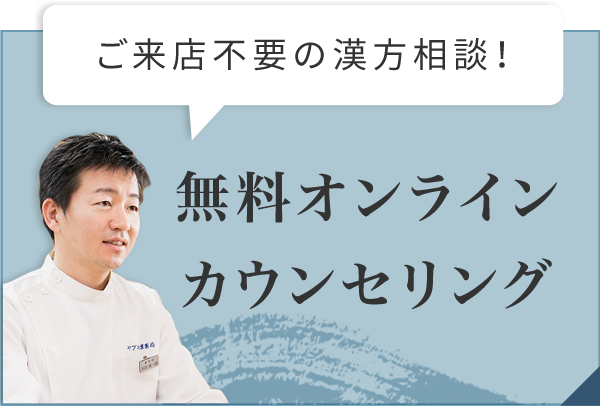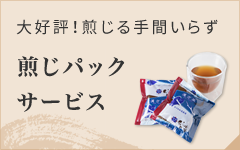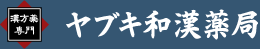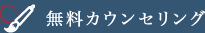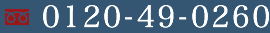「正月うつ」気だるさはなぜ起こる
2023.01.14

新年早々やる気が出ない…
正月休みが終わり仕事も始まっているのに、 無気力状態でなんだかモヤモヤする…
そんな方はいらっしゃいませんか。
自律神経の乱れ
正月休みに、夜更かしや寝坊などによって、普段の生活リズムからの乱れによるもの。
正月休みに食べては寝ての繰り返しで、 1日中ダラダラと過ごすと、 「活動と休息」に切り替える自立神経が乱れてしまいます。
正月休みが長くなればなるほど、 休み明けに「活動状態」に切り替えようとしても、 体や心がなかなかついていかないのは、 自律神経の乱れから「活動と休息」を切り替える スイッチがうまく働かないからです。
日が短くなると発症する「冬季うつ」の一種
「冬季うつ」は、日が短くなり日照量が減ると 「幸せホルモン」と呼ばれる神経伝達物質のセロトニンが 減少することで発症すると考えられています。
セロトニンが不足すると、無気力になったり、 甘いものを過食したり、朝起きれなくなったり… 不安やストレスを感じやすくなります。
これらの要因が重なって、 正月明けに気だるさを感じる人が多いのです。
●朝日を浴びる
「冬季うつ」の要因のひとつ、日照不足の解消に、 起床後2時間以内には朝の日差しを浴びましょう。
寝室は遮光カーテンをかけずに朝日で目覚めるのがベスト。 朝日を浴びると脳内でセロトニンが分泌されます。
朝、散歩したり、通勤もできる限り歩くなど、 朝の光を浴びられるように30分くらい歩くようにしましょう
●幸せホルモンを増やす食事
幸せホルモンのセロトニンは、その材料となる トリプトファンが体内で生成できないので、 食事から補いましょう
【トリプトファンが多い食品】
・大豆製品(豆腐・納豆・味噌 など)
・乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ など)
・卵
・バナナ
・赤身の魚(まぐろやかつお など)
「正月うつ」の解消には、 早寝早起きや栄養バランスの良い食事など、 生活のリズムを整えることが大切です。
やる気がでないときは、少しだけ早起きをして、 朝のリラックスタイムを心がけてましょう
正月休みが終わり仕事も始まっているのに、 無気力状態でなんだかモヤモヤする…
そんな方はいらっしゃいませんか。
自律神経の乱れ
正月休みに、夜更かしや寝坊などによって、普段の生活リズムからの乱れによるもの。
正月休みに食べては寝ての繰り返しで、 1日中ダラダラと過ごすと、 「活動と休息」に切り替える自立神経が乱れてしまいます。
正月休みが長くなればなるほど、 休み明けに「活動状態」に切り替えようとしても、 体や心がなかなかついていかないのは、 自律神経の乱れから「活動と休息」を切り替える スイッチがうまく働かないからです。
日が短くなると発症する「冬季うつ」の一種
「冬季うつ」は、日が短くなり日照量が減ると 「幸せホルモン」と呼ばれる神経伝達物質のセロトニンが 減少することで発症すると考えられています。
セロトニンが不足すると、無気力になったり、 甘いものを過食したり、朝起きれなくなったり… 不安やストレスを感じやすくなります。
これらの要因が重なって、 正月明けに気だるさを感じる人が多いのです。
「正月うつ」を解消するには
●朝日を浴びる
「冬季うつ」の要因のひとつ、日照不足の解消に、 起床後2時間以内には朝の日差しを浴びましょう。
寝室は遮光カーテンをかけずに朝日で目覚めるのがベスト。 朝日を浴びると脳内でセロトニンが分泌されます。
朝、散歩したり、通勤もできる限り歩くなど、 朝の光を浴びられるように30分くらい歩くようにしましょう
●幸せホルモンを増やす食事
幸せホルモンのセロトニンは、その材料となる トリプトファンが体内で生成できないので、 食事から補いましょう
【トリプトファンが多い食品】
・大豆製品(豆腐・納豆・味噌 など)
・乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ など)
・卵
・バナナ
・赤身の魚(まぐろやかつお など)
「正月うつ」の解消には、 早寝早起きや栄養バランスの良い食事など、 生活のリズムを整えることが大切です。
やる気がでないときは、少しだけ早起きをして、 朝のリラックスタイムを心がけてましょう